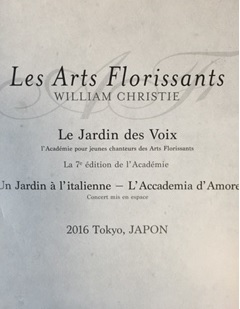
クリスティとレザールフロリサンは、私の知る限りでは初来日となる。私がはじめてこのアンサンブルを聴いたのは、30年以上前。モンテヴェルディの後期マドリガーレ集のCDだ。その音は、いまよりももっと若々しく、荒削りでもあった。今回の、円熟と余裕の演奏をじかに耳にして、時間の流れを大きく感じたのも事実だ。規模の大小はあるが、ほぼ声楽曲のレパートリーに限定されているのは他の古楽アンサンブルと違いの際立つところだが、ハイドンなど古典派の作品も取り上げるようになったのは、ひとつの趨勢とも言えるのだろう。
今回のプロジェクトは「声の庭・イタリアの庭で〜愛のアカデミア」と題される。6人の歌手は譜面を持たない。舞台装置はなく、特別な衣装も身に着けないが、ステージ上で演技を伴って歌うセミ・ステージ形式。プロジェクト名のとおり、イタリアを中心とした、またはイタリア語のオペラ、オラトリオなどによって構成されている。
それは良く出来た流れだ。
いくつかの独立した作品の一部のアリアや多重唱がプログラムされるのは、演奏会としては一般的だが、その内容が繋がっていて、最終的にひとつの物語をなしている。
二部構成のうち、前半はバロックのレパートリーから。ストラデッラ、ヘンデル、ヴィヴァルディ等の楽曲からなり、テーマは愛の裏切りとその苦悩、怒り。そして慰め。
白眉はヘンデル『オルランド』の有名な一場面。愛する女性の気持ちが他の男に移ったことを知った騎士オルランドが、ショックの余り精神に異常を来たし、魂の抜け殻となって地獄を逍遥する。冥府の番犬ケルベロスを幻視し、プロセルピナの同情の涙に慟哭する。5拍子という特異なリズムが、会場全体を一気に緊張の極みまで持っていく。
後半はチマローザ、ハイドンなどの古典派を集めた。
テーマは「劇場支配人」だ。花形歌手の専横に辟易とする18世紀の音楽プロデューサーの姿をユーモアをまじえて描いてゆく。いっぽう、そこでは劇中劇のスタイルで、前半の愛憎劇を受けた男女の情愛についての教訓がまことしやかに語られる。
ラストは再びオルランドが登場する。ハイドンのオペラ『騎士オルランド』から。「幸せになりたいのなら、愛してくれる人を愛せ」と、<愛の学校=アカデミア>を締めくくる。
劇場音楽家としてのクリスティの面目躍如であろう。